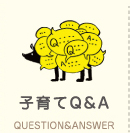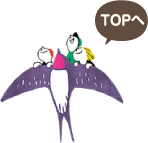問いかけは重い
「学校内外で暴れる。壊す・・・10万件超え」という新聞報道があった(11月18日、朝日新聞)。特に小学生が約7万件と突出している。不登校34万人(小中学生)と合わせて、学校環境のあわただしさが窺える。
子どもが通う学校の前には乳幼児園がある。乳幼児園の前には家庭がある。全ては一本の線でつながっている。学校での問題行動は文科省がデータを集めて、数値化され公表される。しかし、乳幼児園、および家庭の問題行動は数値化されにくい。よくわからないまま闇の中にある。ただし、全てが一本の線でつながっていることに変わりはない。
そして、全ての出発は家庭にある。私達の仕事は家庭に近いところにその存在意義がある。あくまで集団保育、教育だが、子どもライブラリーは専門家集団を自負している。個別対応を丁寧につきすすめると家庭に行き着く。
「言葉で気持ちを表現するのが苦手な子が多い。」というのが、学校内外での暴力の原因のひとつとされる。要するに、年齢に応じたコミュニケーション能力が育っていないということだろう。「言葉」が未発達、未成熟ということだ。
「言葉」が発達、成熟して自在に使えるようになるためには、「言葉を習得する」前の子育て環境が大切になる。
初めから「話せる」子どもはいない。言葉はその音も意味も、そして発音する筋肉運動も、全てつくられる。
「気持ちを表現するのが苦手な子ども」は、言葉を獲得する前に気持ちをわかってもらえる機会の乏しかった子どもと言える。「はじめに言葉ありき。」ではない。「はじめに気持ちありき。」なのだ。
言葉の未成熟な乳幼児は、気持ちを表現するのに体中のあらゆる器官を使って、周りの大人(主に父母)に合図を送る。周りの大人(主に父母)は、それをきちんと受け止め、応えてやらねばならない。これを応答性と呼ぶ。そこに子どもと大人(主に父母)の絆とも言える信頼関係が生まれる。これが「非言語的コミュニケーション」の正体だ。
この応答性が、子どもに「わかってもらえる」という安心感と、伝わることによる自信や自己肯定感を育むことになる。
こう考えると、たとえば「言葉で気持ちをうまく伝えられない。」のであれば、語彙を増やし、言葉のやりとり、会話の練習を・・・と思いつくが、おそらくそれでは期待したほどの効果を生み出さないだろう。問題の本質は、「言葉」以前の信頼関係や自分への自信や自己肯定感だということがわかる。
さて、ここで私達の仕事にもどろう。
10㎞ハイキングの前日に、子ども達は「八丈岩山登山」に挑戦した(3歳児以上)。恒例とは言え、初めての子どもは多い。最近の子ども達は坂道やデコボコ道を歩くことがない。早く歩くことに自信を持っている子どもも、今回は勝手が違う。足の裏の感覚の違和感にとまどう。
また山の急な坂道は、体の使い方、足の運びがいつもと異なる。しかも、これらは教えられない。教則本もない。自分の体で体験して覚えるしかない。楽し気にスイスイ登る子どももいれば、顔がひきつって先生の助けを求める、中には途中で天を仰いで大泣きする子もいる。ただ、どのような状態であっても、先生の助けは限られる。「声を出して励ます。」「手をつないで引っ張り上げる。」最後におんぶされる子もいたが・・・。
ところが登りきると、頂上ではみんないい顔になる。けっこう見晴らしが良い。さわやかなちょっとした驚きの表情がとても可愛い。
ところで山登りは、必ず下りねばならない。これがまた、子どもにはとんでもない冒険になる。坂道は登りより下りがきつい。厳しい。体の筋肉も全く違う部分を使うので、思い通りにならない。どうしても困ったら、お尻を地面につけてすべり降りるしかない。(これはやってみるとけっこう楽しい。しかしズボンは破れる。)
何とか山を下りて、いつもの平地、道路にもどると、子どもはケロリとする。大泣きしていた子、引っ張られ、檄を飛ばされていた子どもも、「何かありましたか?」という表情で、ケロリと涼しい顔をして園にもどってくるのがおもしろい。
さて、私達はこの「山登り」から多くのことを学ぶ。子どもは何を体験しているのか?何を獲得しているのか?を見落とさないように気を配る。楽し気に笑うのも、緊張で顔が引きつるのも、天を仰いで泣くのも、頂上で遠くを見る驚きの顔も、子ども達の貴重なひとつの表現だ。これを見逃すわけにはいかない。どれだけ多くの言葉を使って説明するより、その時の子どもの内面の豊かな気持ちを雄弁に語っている。これを見逃すのは勿体ない。
私達大人は、常に子どものそばにいる。子どもから発せられるあらゆる合図(表現)を大切に受け止める責任がある。そのことがやがて「言葉」を信じられる子どもに育てる。そして学齢期になって、自分の気持ちを表現する言葉を生み出す、学習能力の高い子どもに育つ。「学校内外で暴れる・・・」の問いかけは重い。
出発は産まれ落ちた親のそばから、親が作り出す。家庭から始まる。やがて、私達の手許にやってきた子ども達。集団保育・教育の視点から、親と一緒に私達は子育てに関わる。学齢期までの6年間を侮らず、大切に大切に共に過ごせるように、あらゆる機会を提供して、子育てを充実させたいと考える。
2024/12/09