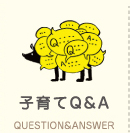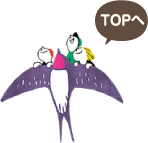2025年夏、アオテアロアは快晴 *アオテアロア:白い雲のたなびく島。ニュージーランド国。
ニュージーランド38回目の学校訪問。7月26日。朝8時、気温18℃。晴。快適だ。さすがに3日目ともなると、生徒のホームシックの連絡もない。到着時の混乱も落ち着いて、静かな週末の朝を迎えた。
私は、ウォーター・フロントの常宿の2階のベランダから海を見ている。目の前を散歩の人と犬が行き交う。リードの無い犬は飼主の前後を自由に戯れる。時々海に飛び込んでまた主人の後を追う。静かで多くのモノは動かない。コトは起こらない。海岸沿いをランニングする人がベランダの先に現れて、端に消えていく。
「さて、今日は10時学校集合。」それまでの時間がたっぷりある。車を走らせて、ヨットハーバーの馴染みのカフェ「アラタイ」に行く。一年振りだ。ガラス張りのフロアから海とヨットが目の前に見える。いつもの「ベーコンエッグ」の朝食と久しぶりのカフェラテを注文する。4人席にひとりでのんびり座って5分待つと、見慣れた「ベーコンエッグ」が運ばれてきた。いくつもあるテーブルには、朝食を摂りに、またランニングの休憩にと、人々がテーブルを囲んでいる。
ほとんど全員しゃべっている。笑っている。ずーっとしゃべる。ずーっと笑う。「カフェを楽しむというのはこういうことだ。」と再認識する。黙って下を向いて小さな機械をいじって・・・。なんて風景はここにはない。人が集まると会話を楽しむ。それが彼らの流儀なのだろう。海沿いのカフェにはその方がよく似合う。
テーブルの下には犬がいる。いつまでも座っている。店の中に動物の気配がない。やがて主人が立ち上がると、はじめて動き出す。それも気持ち良い。
「アラタイ」の隣に新しいカフェ「シナモン」ができている。
B.B.I スクールの校長、ダイアンに言わせれば、「シナモンの方が良い」。 2つの店を見比べると、どうやら「アラタイ」はカラード系の人が多い。それに対して「シナモン」はホワイト系の人が中心。エスプレッソの味が違うと言われるが、どうも私にはその違いがわからない。ワインを飲む時、「シャドニー」「ピノノア」「スーベニア」・・・とブドウの種類で好みを言い合うのが彼らの楽しみ方だが、それも私にはよくわからない。
しかし、「タイ米」と「日本米」の違いは彼らにはよくわかっていない。そこは私の領分だ。
40年近く同じ地域、同じ学校と交流を続けていると、他国とは言えいろいろな歴史の変遷も経験できる。変わらないのは学校のシステムと人の生き方だろうか。
N.Z人口500万人のコンパクトな国だ。学校を中心として多様な職種の人と出会うことができる。私は毎晩ホームパーティーに呼ばれて、いろいろな家庭を訪問させていただく。まず、どの家もパラス(宮殿)のようで驚くのは毎回のこと。そこに集う人達がまたさまざまで刺激的だ。
現役の有名ミュージシャンとワインを飲んでデュエットしたこともあれば、経済のスペシャリストに世界経済のレクチャーを受けたこともある。
エアーニュージーランド(国営航空)の幹部は私達の帰国時、飛行機のコックピットに私あての「グッバイメール」を送ってくれた(そんなことしていいのか?)。またある時は、到着した日本の空港で「マサ」と呼び止められた。制服のキャプテン(機長)がサングラスを外すと、ホームパーティーで一緒に飲んだ・・・。「これはオレの飛行機だ。」と彼がニッコリ。世界とつながる偶然は楽しい。
今回はラグビーリーグ。T.Vの解説者の手配で、私はオンザフィールドでT.Vのクルーと一緒に3万人のスタジアムでラグビーの観戦をさせてもらった。(彼は20年前の有名なプロラグビープレーヤー。キャプテン。今も有名でスタジアムの中で何度もサインを求められていた。私はその後ろをおっかなびっくりでついていく。)ステキなアナウンサーとの写真は早速額に入れた。
「私の甥がオペラ歌手だ。素晴らしい家だ。今度ワインを飲もう。マサの孫が来たらホームステイさせてやるから、連れて来い。」と言われたが、いきなりその環境も「どうかな~。」と考えるのは、日本人的な私の小さな気遣いのようだ。彼らはいつも「人生を楽しむ」ということを基準に考える。決して贅沢という発想ではない。
日本の子ども35名は、毎日学校に行く。授業を受ける。1日3コマ(1コマは100分)は、ちょっとキツイか・・・と。午後はアクティビティに貸切バスで連れ出す。
私達のグループは学校の協力で「バディ制度」を採っている。(この方法は、日本の海外向け旅行会社も驚く。全国でも例のないシステム。)
最近は、韓国、中国からの留学生も随分増えたが、バディシステムはしてもらえない。長年の積み重ねと交流による信頼の賜物と学校関係者には感謝しかない。
ホームステイはバディがいる家。現地の親は日本の子どもを自分の子どものようにかわいがってくれて、大切にしてくれる。具合の悪い時も安心して任せることができる。
今回の参加者は、初めて全員「スマホ禁止」とした。スマホは低年齢の子ども達にとっては、百害あって一利なし。いろいろな考え方があるのは承知している。しかし、結果として良かったと思う。子ども達は充分それに順応できていたし、スマホに絡むトラブルもなく、まず自分の目で見る、耳で聞く、そして考えるというスッキリとした外国体験ができていた。
もっと検索をして知識を深めたい、もっと翻訳機能を使ってコミュニケーションをしたい。というのは、次のステップでいいと思う。とにかく日本の子ども達は世間知らず。自分の五感で受け止めるところから始める。という意味で、「スマホなし」は有効だった。
・・・にしても、忘れ物が多かった。「カメラ・帽子・衣類・財布・さらにパスポート」。その度に多くの人に探していただき、戻すのにお世話になった。本当に申し訳ないことだった。
しかし、当の本人はケロリとして、それほどあわてるわけでもなく、「ハァー」という顔をしている。自分の持ち物に対する愛着、責任の感覚が身に付いていない。これは学校体験以前の問題。日々の家庭生活の中での訓練が足りないのだと思う。「誰かが何とかしてくれる」という他力の甘えは、他国では全く通用しない。この点は反省して欲しい。子どもだけでなく家族全員で・・・。
最後に、今年は在オークランド総領事(Cousulate General of Japan in Auckland)の松居氏が私達の学校歓迎会に臨席され、国を代表してスピーチをいただいた。(外務省の公式ホームページにアップされています。皆さんチェックして下さい。)
名誉なことと考えている。多くの人に、また国の機関に関心を持っていただいて、この学校交流事業が続くことを願っている。(子どもライブラリーは先進的、斬新な教育・保育の実施園として、国の内外で注目されています。うれしいことです。)
私は帰国後の8月8日、姫路市教育委員会の久保田教育長に、外務省のホームページと歓迎会の校長達との写真を持って、報告のための面談をした。(小さな羊のぬいぐるみを持参しました。)そして、今後の学校交流の協力をお願いした。
いろいろな方のお世話になっていることを忘れず、さらなる発展を目指していきたい。
2025/09/09