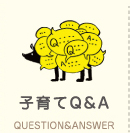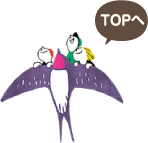見えるものに答えはない
園舎は完成して、外構も間もなく終了。
「TIKIのいるカフェ」はウッドデッキと駐車場の舗装を残すのみとなった。仕上がるとキレイ。ゴウカで気持ちが良い。丁寧に細かく手をかければかけるほど味わいも深い。
私はその仕事のプロセスを見ていた。職人がひとつひとつ手をかけて、作っていく。地形によっては、ああでもない、こうでもないと思案を重ねる。半日かかって殆どすすまないこともあった。
完成すると、どこをどのように工夫して手をかけてきたのかは、わからなくなる。いま目に見えているものが全てだ。そこに評価が集まる。しかし・・・・・と思う。目に見えないものにこそ技がある。それを支える背景が隠されているものだ。
建築は子育てに似ている。共有できる学びは、「目に見えるものに答えはない。」ということだろう。
新学期から2カ月が経った。グループ懇談会も終わって、子ども達はステップアップの時期に入る。子どもの育ちについて、見えない資質について、保護者と共有するのはむつかしい。今日の子どもは、昨日の子どもの結果だ。3か月前の子どもと地続きでつながっている。ということは、今日の子ども理解は、いま目の前のそこにはないということになる。子どもの姿を理解するのは簡単ではない。その分析には多様な視点が必要だ。
たとえば、朝泣く子どもがいる。私は「お母さん、お父さん、大好き。」で別れるのが悲しいのではないと説明した。不安現象だと解説した。さらに不安現象の源は学習不足。そして学習は「見る力」「聞く力」の蓄積だと分析する。
しかし、そのようなわけのわからん話は、まあどうでもいい。それよりも、みんなはどうしたらいいのかを知りたい。それが泣き続ける我子への親心だ。
=不安現象ということであればより可愛がる。より大切にする。親替わりとなる先生を見つけて託す。本人が安心できる状況を早く用意してあげるのが、解決の方法となる。=
しかし、これでは明日はとりあえずうまくいったとしても、本質は変わらない。子どもの力は育たない。「ようやく慣れましたね。」という言葉に、軽々に飛びつくわけにはいかない。
目標はいつも「自分ひとりで生きていけるように育てる。」ということ。となると、自分の力で不安を取り除き、自分の力で現状を乗り越えていけるような力を育てたい。
そのためには、不安現象の源泉になっている「学習不足」を考えることは、必須となってくる。
私は次に子どもをよく観察しようと付け加えた。
朝、親と別れる時に泣く子どもは一様ではない。「親にしがみつく子」「泣きながらでも先生の方に両手をのばす子」「長泣きする子」「あっさり泣きやむ子」「3日間続く子」「1週間経っても泣き続ける子」「ふりしぼるように泣く」「涙は出ない声だけで泣く」・・・等々。
ちょっと思いつくだけでも、「泣き方」にもいろいろある。それは子どもひとりひとりの内面の育ちをあらわしている。全く複雑だ。これが親や先生を混乱させる。
こう考えると、「学習不足」としても、ひと言で解決の道筋は描けない。もっともっと不思議な子どもの内面に分け入って、かくれている秘密を探し当てる努力をしなければならない。そのためには、子どもをよく見る(観察する)ことが大切だ。子どもから発信される、あらゆる合図を見落としてはならない。この場合、「言葉の説明」はむしろ邪魔になる。言葉にならない言葉の世界。つまり「非言語的コミュニケーション」の世界への親和性こそが大切になる。はじまりは、「何のことかわけわからん」でもかまわない。とにかく、子ども(我子)に興味・関心を持って、何も言わず(これが大切)見続けることだ。
たったひとつのテーマでも、こんなに頭がクラクラするような熟考が求められる。また、子どもの姿は万華鏡のように瞬時に変化する。その変化についていけるだけの思考力と感性も必要だ。
今回のグループ懇談会でも、いろいろ話し合った。共有できたこと、できなくて反発が生まれたものさまざまだ。
しかし、どの子どものことを考えるのも手抜きは許されない。無難に適当に話を合わせて、「やりすごして」涼しい顔もできない。それが保育者としての矜持であり、保護者への責任であり、幼児学舎子どもライブラリーの真骨頂でもある。
5月後半になって随分と子どもも変化している。特に問題行動を抱えていた子どもの変貌は著しい。うれしいことだ。大人が前を向いて、こだわらず現実を受け入れれば、子どもは美事に変わっていく。一方で、大人が執着して変わらなければ、間違いなく子どもは停滞する。保護者と共に前に進むために、心身共にまみれる努力は惜しまないようにしたい。
2025/06/12